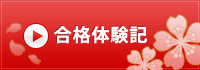現役合格おめでとう!!
2025年 田無校 合格体験記

明治大学
商学部
商学科
鶴田菜々子 さん
( 錦城高等学校 )
2025年 現役合格
商学部
私は高校2年生の3月に東進に入学しました。東進に入るまで、学校の定期テストの勉強しかしたことがなかった私は基礎の基礎から勉強を始めました。春休みは1日に2コマ以上受講し、とにかく勉強する習慣を身につけました。
しかし、世界史が苦手だった私は1番最初に受けた共通テスト本番レベル模試では4割しか取れず、危機感を覚え、そこから毎日世界史の教科書や用語集を表紙が剥がれるまで反復しました。夏休みは毎日開館登校、閉館下校を心がけ、過去問も10年分ときました。その結果本番の世界史では過去最高の90点まで点数を上げることができました。
この受験生活を通して大事だと思ったのは最後まで基礎の反復を怠らないことです。私は受験の直前まで英単語帳や古文単語帳を欠かさず開くようにしていました。毎日使った単語帳をみると当日の自信にもつながり、落ち着いて試験に臨むことができました。
この1年を通して得られたことがたくさんありました。受験は自分を成長させることができるとてもいい機会だと思います。諦めずに志望校に向かって走り続けることは必ず大きな自信になると思います。大学では受験で培った努力する姿勢を持ち続け、自分のやりたいことを見つけられたらいいなと思います。
しかし、世界史が苦手だった私は1番最初に受けた共通テスト本番レベル模試では4割しか取れず、危機感を覚え、そこから毎日世界史の教科書や用語集を表紙が剥がれるまで反復しました。夏休みは毎日開館登校、閉館下校を心がけ、過去問も10年分ときました。その結果本番の世界史では過去最高の90点まで点数を上げることができました。
この受験生活を通して大事だと思ったのは最後まで基礎の反復を怠らないことです。私は受験の直前まで英単語帳や古文単語帳を欠かさず開くようにしていました。毎日使った単語帳をみると当日の自信にもつながり、落ち着いて試験に臨むことができました。
この1年を通して得られたことがたくさんありました。受験は自分を成長させることができるとてもいい機会だと思います。諦めずに志望校に向かって走り続けることは必ず大きな自信になると思います。大学では受験で培った努力する姿勢を持ち続け、自分のやりたいことを見つけられたらいいなと思います。

明治大学
文学部
史学地理学科/地理学専攻
大場崇司 くん
( 明治大学付属中野高等学校 )
2025年 現役合格
文学部
僕が大学への内部進学を目指して東進に入ったのは高1の12月で、その時の成績は10段階で5点台と悲惨でした。はじめのうちは高速マスター基礎力養成講座や受講などを進めていましたが、1つの教科が上がると別のものが下がってしまい、思うように成績が上がりませんでした。そんな中、高2の2学期ごろから定期テスト専用の対策が開始され、担任助手の方が教科ごとについて対策をしてくださるようになってから徐々に成績が上がり、高3の初めに10段階で7.8という個人的には過去最高の成績を取れてから勉強のスタイルを確立し、最後の試験では8.3を取り、なんとか推薦の枠に入り込むことができました。
勉強癖もなく課題もあまりやってこない僕に発破をかけ大学合格まで見守ってくださった担任の先生には感謝の気持ちでいっぱいです。しかも、自分の第一志望の学科に合格することができ、本当に感謝しかないです。僕は家にいると寝る前の単語やプリント以外は勉強しない人だったので、東進に行くことで無理やりスイッチを入れて勉強していました。その東進に行くのも億劫で約束の時間を過ぎて登校したこともありました。それでも見捨てず声をかけてくださった結果、長期休みは毎日登校、それ以外でも定期テスト1か月前から毎日登校をするなど意識を高めていくことができ、大学にも合格することができました。
第一志望の学科は地理系の学科で、僕の場合北海道の衰退した都市について興味を持ち、都市についてもっと詳しく学びたいと思っており、将来は地方創生に関わる仕事がしたいなと考えています。
勉強癖もなく課題もあまりやってこない僕に発破をかけ大学合格まで見守ってくださった担任の先生には感謝の気持ちでいっぱいです。しかも、自分の第一志望の学科に合格することができ、本当に感謝しかないです。僕は家にいると寝る前の単語やプリント以外は勉強しない人だったので、東進に行くことで無理やりスイッチを入れて勉強していました。その東進に行くのも億劫で約束の時間を過ぎて登校したこともありました。それでも見捨てず声をかけてくださった結果、長期休みは毎日登校、それ以外でも定期テスト1か月前から毎日登校をするなど意識を高めていくことができ、大学にも合格することができました。
第一志望の学科は地理系の学科で、僕の場合北海道の衰退した都市について興味を持ち、都市についてもっと詳しく学びたいと思っており、将来は地方創生に関わる仕事がしたいなと考えています。

明治大学
文学部
文学科/日本文学専攻
大谷昂生 くん
( 明治学院東村山高等学校 )
2025年 現役合格
文学部
僕が明治大学文学部に合格できたのは、4月に部活を引退してから覚悟を決め、ほとんど毎日東進に通うことができたからだと思います。4月に部活の大会が終わり、部活をしていた時間を東進での勉強に充てることができるようになりました。その時から自分の行きたい大学に行くにはどのように生活すればよいか考えました。考えた末、今のままでは到底、志望大学は言うまでもなく、それよりも偏差値が低い大学にも合格できないと思い、東進に毎日通うことを決意しました。
その後、東進に毎日通う日々が続きましたがなかなか結果が出ず、何度も不安な気持ちに苛まれました。それでも自分を信じて、夏休みはほとんど毎日朝の9時半までに登校し、駅の近くにある飲食店で食事を済ませ、夜の9時半頃まで東進で勉強をしました。
ここまでできたのは志望大学に合格したいという強い思いがあったからだと思います。夏休み明け頃から自分でも成績が向上し始めたという実感が湧きました。しかし、判定は相変わらず悪いままでした。ここでくじけたら一生後悔するという思いで12月まで東進に行きました。この逆境もいつしか自分の利益になると思い続けました。そして僕は英語が不得意だったので国語、英語、社会が同じ配点の大学・学部をできるだけ選んで受験しました。
受験当日も、もう後悔はないと思いながら受験しました。結果、明治大学文学部に合格できました。受験当日の自信は1年間、挫けず、毎日東進に通うことができたことだと思います。
その後、東進に毎日通う日々が続きましたがなかなか結果が出ず、何度も不安な気持ちに苛まれました。それでも自分を信じて、夏休みはほとんど毎日朝の9時半までに登校し、駅の近くにある飲食店で食事を済ませ、夜の9時半頃まで東進で勉強をしました。
ここまでできたのは志望大学に合格したいという強い思いがあったからだと思います。夏休み明け頃から自分でも成績が向上し始めたという実感が湧きました。しかし、判定は相変わらず悪いままでした。ここでくじけたら一生後悔するという思いで12月まで東進に行きました。この逆境もいつしか自分の利益になると思い続けました。そして僕は英語が不得意だったので国語、英語、社会が同じ配点の大学・学部をできるだけ選んで受験しました。
受験当日も、もう後悔はないと思いながら受験しました。結果、明治大学文学部に合格できました。受験当日の自信は1年間、挫けず、毎日東進に通うことができたことだと思います。

明治大学
商学部
商学科
大澤綾 さん
( 武蔵高等学校(都立) )
2025年 現役合格
商学部
私は高校2年生の春に東進に入りました。高校1年生のときは勉強習慣がなく、テスト前に詰め込むタイプで成績も悪く、親に東進を勧められたことが入学のきっかけでした。
高校2年生のときは、部活終わりに校舎に来て高速マスター基礎力養成講座と受講を主に進めていました。友達と放課後に遊ぶこともありましたが、予定のない日は必ず登校することを心がけていました。高速マスター基礎力養成講座は、冬までに上級英単語を終わらせることを目標に進めました。達成後の共通テスト同日体験受験では、英語の成績を12月から40点程度上げることができ、英語に対する苦手意識が克服され自信に繋がりました。
受講は、古典と数学、英語、日本史を主に学習しました。高校3年の6月までに終わらせて演習に入ることを目指し、春休みには1日に2、3講座受講していました。高校3年生になってからは、土日祝には友達と一緒に開館登校を欠かさずにしました。
また、春に部活を引退してからは学校が終わるとすぐに東進に行き、平日でも7、8時間勉強していました。6月からは共通テスト演習を進めました。8月の本番レベル模試に向けて、苦手分野を無くすために大問別演習に徹底的に取り組み、1つ1つ解消していきました。
その結果、今までE判定だった第1志望校が8月の模試ではB判定になり本当に嬉しかったです。秋には最後の学校行事に取り組みながらも、志望校別単元ジャンル演習講座のセットを進めました。志望校別単元ジャンル演習講座ではやった分だけ向上得点やランキングにつながり、結果が可視化されることが自分の性格に合っていてモチベーションになりました。
12月からは共通テスト対策に取り組み、模試やパックを中心に進めました。10年分以上取り組んだおかげで、共通テスト本番でも模試のような感覚で、あまり緊張せずに受験することが出来ました。最終的には合計で9割を得点し、その後の志望校対策に向けて前向きに取り組むことが出来ました。
高校2年生のときは、部活終わりに校舎に来て高速マスター基礎力養成講座と受講を主に進めていました。友達と放課後に遊ぶこともありましたが、予定のない日は必ず登校することを心がけていました。高速マスター基礎力養成講座は、冬までに上級英単語を終わらせることを目標に進めました。達成後の共通テスト同日体験受験では、英語の成績を12月から40点程度上げることができ、英語に対する苦手意識が克服され自信に繋がりました。
受講は、古典と数学、英語、日本史を主に学習しました。高校3年の6月までに終わらせて演習に入ることを目指し、春休みには1日に2、3講座受講していました。高校3年生になってからは、土日祝には友達と一緒に開館登校を欠かさずにしました。
また、春に部活を引退してからは学校が終わるとすぐに東進に行き、平日でも7、8時間勉強していました。6月からは共通テスト演習を進めました。8月の本番レベル模試に向けて、苦手分野を無くすために大問別演習に徹底的に取り組み、1つ1つ解消していきました。
その結果、今までE判定だった第1志望校が8月の模試ではB判定になり本当に嬉しかったです。秋には最後の学校行事に取り組みながらも、志望校別単元ジャンル演習講座のセットを進めました。志望校別単元ジャンル演習講座ではやった分だけ向上得点やランキングにつながり、結果が可視化されることが自分の性格に合っていてモチベーションになりました。
12月からは共通テスト対策に取り組み、模試やパックを中心に進めました。10年分以上取り組んだおかげで、共通テスト本番でも模試のような感覚で、あまり緊張せずに受験することが出来ました。最終的には合計で9割を得点し、その後の志望校対策に向けて前向きに取り組むことが出来ました。

明治大学
経営学部
経営学科、会計学科、公共経営学科
本間彪雅 くん
( 錦城高等学校 )
2025年 現役合格
経営学部
僕が東進に入った理由は同じ部活の人が続々と東進に入っているからでした。3年生の5月になり部活の引退も近づいてきた頃、僕は勉強面の方がかなりピンチであったことに焦っていました。今までは「部活で疲れた、部活が夜遅くまで続くから勉強できひんわ!」などと言い訳できたのですが、もうすぐ引退となったことによりそれが通じなくなることは明らかでした。仲間もそれを感じていたのか、この時期から僕たちは勉強を始めました。
そんなこんなで東進に入学することとなり、最初の週は黙々と勉強していました。しかし、2年間のブランクがあった僕にそんな集中力などあるはずもなく、次の週ではもう勉強したくないゾーンに入ろうとしていました。その時、転機が訪れます。
それが東進特有のシステムである「チームミーティング」です。ここで出会ったY君が同じ高校の人であることが分かりすぐに意気投合、僕は勉強のペースを徐々に上げることができたと思っています。これを機に僕の学力はぐんぐんと上昇...とはいかなかったものの、ペースが上昇した以上、着実に力を付けていくきっかけとなったのです。
僕が勉強する上で心掛けていることが1つあります。それは勉強に限らず様々な場面で対応できる応用的な知識を獲得することです。勉強は勉強...と実生活と区切りをつけてしまっては意味がない、時間の無駄だと考えています。
そんなのどうやってやんねんと思うかもしれないですが、例えば英語なら語源を知ることで日常生活で見る英語の意味を理解できるようになる、情報科目なら16進数を知って数字の新たな一面を知る、世界史なら今の世界情勢の根本に繋がる原因を知る...など文系理系関わらず方法はあります。
この方法が結果的に自分の勉強のモチベーション維持につながり、合格の原点にもなったと考えています。この方法で今の僕は自信を持てています。今後もこの方法を経営関係の知識につなげていきたいと考えています。
確かに、1人で平気、勉強って一時的なものでしょという意見は否定できませんし、それで結果を出す人もいるでしょう。しかし僕は実績を残し、この方法が有用であることを示したので、勉強無理―!とかもうやだ...と思った人たちは「チームミーティング」、「応用知識の獲得」を意識して勉強することを自信を持っておすすめします。
頑張れ、受験生!!
そんなこんなで東進に入学することとなり、最初の週は黙々と勉強していました。しかし、2年間のブランクがあった僕にそんな集中力などあるはずもなく、次の週ではもう勉強したくないゾーンに入ろうとしていました。その時、転機が訪れます。
それが東進特有のシステムである「チームミーティング」です。ここで出会ったY君が同じ高校の人であることが分かりすぐに意気投合、僕は勉強のペースを徐々に上げることができたと思っています。これを機に僕の学力はぐんぐんと上昇...とはいかなかったものの、ペースが上昇した以上、着実に力を付けていくきっかけとなったのです。
僕が勉強する上で心掛けていることが1つあります。それは勉強に限らず様々な場面で対応できる応用的な知識を獲得することです。勉強は勉強...と実生活と区切りをつけてしまっては意味がない、時間の無駄だと考えています。
そんなのどうやってやんねんと思うかもしれないですが、例えば英語なら語源を知ることで日常生活で見る英語の意味を理解できるようになる、情報科目なら16進数を知って数字の新たな一面を知る、世界史なら今の世界情勢の根本に繋がる原因を知る...など文系理系関わらず方法はあります。
この方法が結果的に自分の勉強のモチベーション維持につながり、合格の原点にもなったと考えています。この方法で今の僕は自信を持てています。今後もこの方法を経営関係の知識につなげていきたいと考えています。
確かに、1人で平気、勉強って一時的なものでしょという意見は否定できませんし、それで結果を出す人もいるでしょう。しかし僕は実績を残し、この方法が有用であることを示したので、勉強無理―!とかもうやだ...と思った人たちは「チームミーティング」、「応用知識の獲得」を意識して勉強することを自信を持っておすすめします。
頑張れ、受験生!!